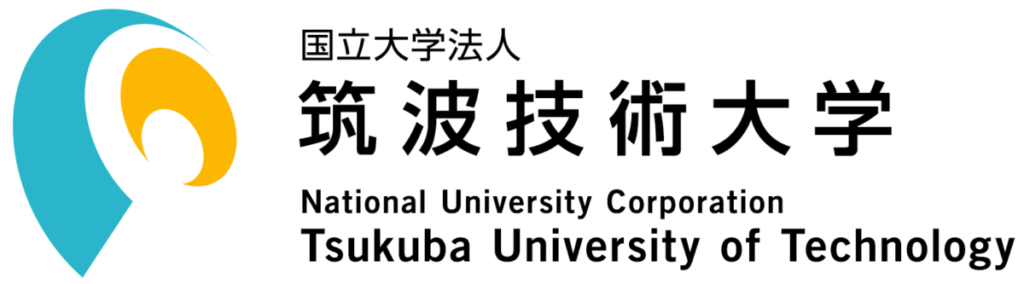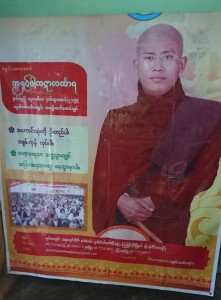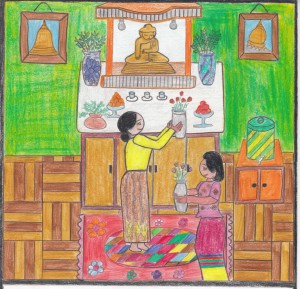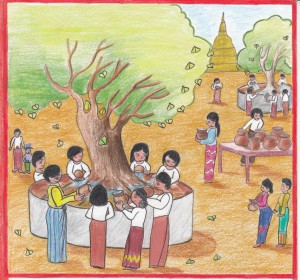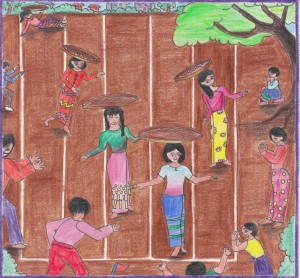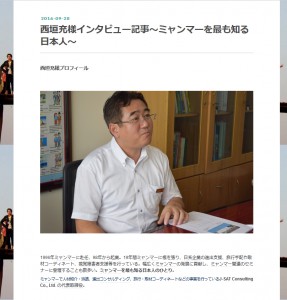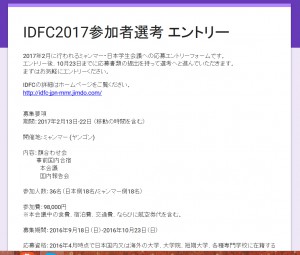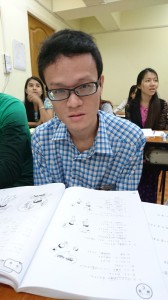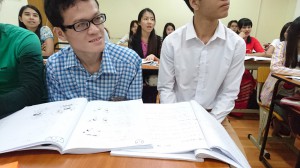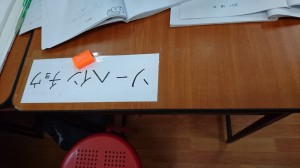2016年10月25日
NPO法人日本ブラインドサッカー協会が協力し ミャンマーで普及活動を実施
「ミャンマーの視覚障害者に新たな夢と希望を」
NPO法人日本ブラインドサッカー協会(以下、JBFA)は、2016年12月13日~16日までの4日間にわたり、ミャンマーでブラインドサッカーの普及活動を実施し、日本選手権4連覇中のAvanzareつくばに所属する川村怜と福永克己を派遣いたします。ミャンマー社会福祉・救済再復興省の招致でミャンマーの中心都市ヤンゴンに来緬。日本代表の選手およびスタッフとしても活動する2人がミャンマーの視覚障害者らにブラインドサッカーの基礎技術を伝えることで、普及を目指します。

ブラインドサッカー
■ミャンマーにおけるブラインドサッカー普及活動実施の経緯
ミャンマーでは統計上で視覚障害者は約18万人、実際には30万~40万人いるとも言われており、家に閉じ籠もりがちの者も多く、ほとんどの者は社会的・経済的に自立していないのが現状です。
2009年から視覚障害者支援を行う株式会社ジェイサットコンサルティング社代表の西垣充が、2011年民政移管後、ミャンマーが急速に発展するも視覚障害者を取り巻く環境はあまり変わっていない現実から、視覚障害者らにも経済発展の恩恵を受ける事業をミャンマー政府側と協議しブラインドサッカー普及活動を提案。視覚障害者支援開始当時から、献身的に協力、指導頂いている、筑波技術大学形井教授及び緒方教授、そしてJBFAの協力により、今回の普及活動が実現しました。今回の日本人指導者2名の費用やヘッドギア、マスク、ゴールポスト、ボール、会場使用費及びミャンマー政府、筑波技術大学との交渉はすべて、株式会社ジェイサットコンサルティング社が単独で負担、コーディネートしています。
■ブラインドサッカーの具体的取り組み予定
ヤンゴン国立チミダイン盲学校、ヤンゴンチミダイン盲学校、ゲンキーマッサージ店の3チームから10名を選出。ブラインドサッカーのルールからパスの仕方など基本的な技術を伝え、各学校、マッサージ店にブラインドサッカーの楽しさを伝え、今後の本格的な普及活動に活かします。最終日は3チーム対抗PK戦を行う予定です。
■ミャンマーでのブラインドサッカーの現状
視覚障害者5人制サッカー(視覚障害者サッカー、通称:ブラインドサッカー)とは、視覚に障害を持った選手がプレーできるように考案されたサッカーです。
これまで、ブラインドサッカーのミャンマー代表は2年前のアセアンパラゲームズ(東南アジアパラリンピック)で、タイ代表、マレーシア代表と戦っていますが、2015年末にシンガポールで開催されたアセアンパラゲームズには不参加でした。また、IBSA(国際視覚障害者スポーツ連盟)には加盟しておらず、近年、視覚障害スポーツではパラリンピックには出場していません。
安倍総理は「ODAなどでスポーツ支援を行っていきたい」と述べ、スポーツ分野の発展途上国支援に積極的に取り組む姿勢を示しており、2020年東京パラリンピックのミャンマー出場も見据えています。
■プロフィール
<川村怜(かわむら・りょう)>
1989年生まれ、大阪府出身。Avanzareつくば所属。
筑波技術大学在学中よりブラインドサッカーを始め、2013年さいたま市ノーマライゼーションカップで日本代表デビューし、世界王者ブラジルから初ゴールを奪う。インチョン2014 アジアパラ競技大会、世界選手権2014、アジア選手権2015などに出場。アジア選手権では、チーム最多となる7得点をマーク。得点力と豊富な運動量でチームを牽引する。
<福永克己(ふくなが・よしき)>
1973年生まれ、大阪府出身。Avanzareつくば所属。
2007年筑波技術大学赴任後よりブラインドサッカーに関わり、2009年GKとして日本代表選出。2010年より日本代表コーチ。現在はAvanzareつくば代表を務める。
■筑波技術大学及びAMINについて
学校名:国立大学法人筑波技術大学
所在地:〒305-8521 茨城県つくば市春日4-12-7
TEL :029-852-2890(代表)
筑波技術大学とは、聴覚または視覚に障害を持つ人が学ぶ4年制国立大学。筑波技術大学が中心となり、アジア医療マッサージ指導者ネットワークAMIN:Asia Medical Massage Instructors Network.の活動も行っています。主にアジア太平洋地域の途上国に、視覚障害者が、医療マッサージの専門家として就業できる体制を整備することを目的としており、2009年からミャンマーにも定期的にセミナーを行い、普及活動を行っています。